どうしてWordはこんなにも使いづらいのか。
Wordを使うたびに、ふと思う。「どうしてWordだけ、こんなに使いにくいんだろう。」
書式は勝手にズレる。メニューはどこにあるかわからない。10年前と同じことで、いつも迷子になる。
最新版がリリースされても、Wordは使いづらいままである。そんなWordに対する「なんでだよ」という気持ち。
今回は、「どうしてWordはこんなにも使いづらいのか」に焦点をあて、深堀してみることにした。
❶ Wordはもともと「タイプライター」ではなかった
Wordの初期設計(1980年代)は、紙に文字を印刷するためのツールではなく、「あらゆる種類のドキュメント」をデジタルで整形・編集するという野心的な発想から出発していた。これは当時のソフトウェアとしては非常に先進的で、たとえば:
- 同じ文書内に複数の「セクション」を持てる
- ページの概念は「出力用の見た目」であり、構造は別に存在する
- テキストの流れ(Flow)とスタイルの適用(Style)を別管理
この思想は、後のLaTeXやHTMLのような「構造と見た目の分離」に近い。 つまりWordは、WYSIWYG(見たまま印刷)でありながら、裏では構造処理ソフトだったのだ。
✔ ここが、パワーポイントやエクセルと決定的に異なる点。
❷ 「すべてを満たす」ことを目指した結果、UIが破綻していった
MicrosoftはWordを、学生・ビジネスマン・学術関係者・法律文書作成者・クリエイター…
すべての用途に1本で応えられる汎用エディタにしようとした。
しかしこれにより、以下のような問題が起きる:
- 目的ごとに必要な機能が全く違う(たとえば章立てと、表組みと、注釈機能は用途が真逆)
- ユーザーの知識レベルがバラバラ(見出しの階層とフォントサイズを混同する人が多発)
- カスタマイズ可能性を高めすぎて、表層のUIでは挙動が読めなくなる
結果として、
「設定項目はあるのに、それがどこにあるのかわからない」
「できるはずなのに、どの方法を選べばいいのかわからない」
という、“実現できるけどアクセスできない地獄”が生まれた。
以降、「どこに何があるか分からない」メニュー画面が随所に発生することとなる。
❸ 長い歴史ゆえの「互換性」という呪い
Wordには「過去に作られた文書すべてを正確に再現できなければならない」という宿命がある。
このため、以下のような「幽霊機能」が今も残り続けている:
- 独自の
.docフォーマットの互換モード(2003年以前のレイアウト) - レガシースタイルや、見えない段落書式
- 表示上見えない「フィールドコード」や「非表示スタイル」
つまり、UIを大胆に刷新することができない。
なぜなら、既存文書を壊さないことが最優先されるから。
これにより、「古い仕様を引きずったままの新UI」が、表層だけモダンに塗り直されて提供される。
それが、現代のWordで「リボンメニューがあっても迷子になる」理由のひとつ。
❹ 機能が“曖昧に連携”しているため、操作が記憶に残らない。
Wordは、明確なコマンド入力型(たとえばLaTeXやマークダウン)ではなく、
GUIでの操作と裏側の構造の差が大きすぎる。
たとえば:
- スタイルを適用したつもりでも、ローカルで上書きされていると見た目が変わらない
- セクション区切りと改ページの違いがわからないまま、崩れたレイアウトだけが残る
- 目次は「自動で生成できる」のに、「それがどの操作によって可能になるか」は直感では理解できない
これは言い換えれば、UIが「操作の理由を説明してくれない」設計になっているということ。
❺ 数億人単位のユーザーの為に。「改善されない」のではなく「改善できない」操作性
Wordには、数億人単位のユーザーがいる。
このユーザー基盤を前提にすると、たとえUIや操作の一部を洗練させたくても、
- 「今のままで慣れている層」が使えなくなる
- 「過去のテンプレが壊れる」などのトラブルが発生する
- 「ユーザーが混乱すること」を恐れて、新しい機能を“オプションとして”しか追加できない
結果として、新旧のUIや設定が“並列して残る”という状態が続いていく。
✔古い機能の保全と、新機能の入り口が分かれることで…
同じような設定が謎に3か所に分散する状態などが発生し、「前できたこと、どうやったっけ…」と思い出せない現象につながる。
記憶に定着しないUI(何度しらべても“身体に馴染まない現象”)が繰り返され、「長年Wordを使っているのに、使うたび使いづらい」という現象が生まれる。
総括:Wordは「全部できる」を目指した“巨大な折り紙”のような存在
Wordは、
あらゆる種類の文書に対応する、1つの万能なデジタルペーパーとして生まれた。
そして、目的に応じて専用のツールを用意した方が効率的である時代に入ってもなお、
「ひとつで全部やる」ことを目指し続けている。こんなソフトは、他にはない。
だからこそ、私たちはときどきその複雑さに戸惑い、
そしてまた、“なんとか工夫すれば使えてしまう”がゆえに、手放すこともできない。
Wordが抱えているのは、
「正しさ」と「親しみやすさ」
「歴史」と「未来」
「多くのユーザーの過去のデータ」を、「未来に保全する信頼性」である。
WordのUIが持つ「非効率さ・構造上の欠陥」は、それらを、1つのソフトの上で同時にかなえようとする矛盾により、生まれたもの。
つまり、「すべてのユーザーの希望に応えつづけ、切り捨てなかった結果」が、今のWordの姿である。
ポッと出の最新ソフトとは、抱えている使命と責任の重さが全く別物なのである。
あなたがWordを「使いづらい」と感じたのは、知識や経験が足りいわけでもない。
でも、Wordが悪いわけでも、開発陣が無能なわけでもない。
Wordそのものが、過去のユーザー(あなたも含む)に寄り添っい、すべてを抱えたまま進化するソフトだからである。
まとめ -10年前の機能に、ありがとう-
1983年のリリース以来、あまりに多くの歴史とユーザーを抱えてしまったがゆえに、「使いやすく進化する」のとは異なる道を進むしかない。Wordは、そんな宿命を背負った存在ということがわかりました。
“改善されていない”のではなく、“改善することができない”。
“「効率的なUI」と、「古い機能の保全」のはざま“
そこに存在するのが、Wordというソフト。
そして、「本当に使いづらい。」と感じながらも、私たちは、Wordを使い続けている。
使い方を工夫し、折り合いをつけ、 なんとかデータを整えながら、「10年前の機能、そのまま残してくれてありがとう」と思ってみるのも、いいのかも知れません。
Wordはきっと、「今日作ったファイル、10年後も開けるようにしとく。頑張るよ。」と答えてくれるのではないでしょうか。

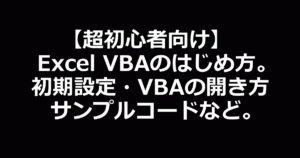
コメント